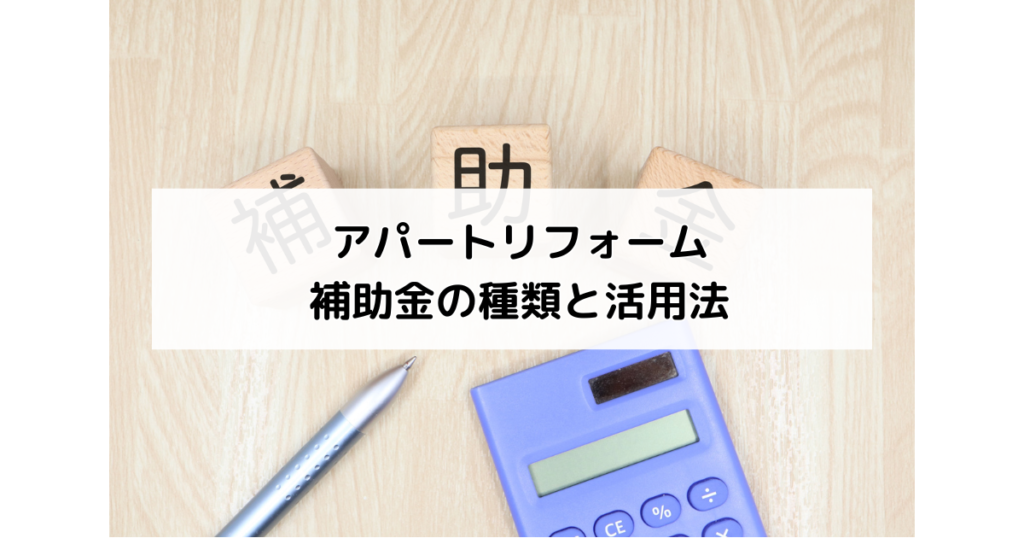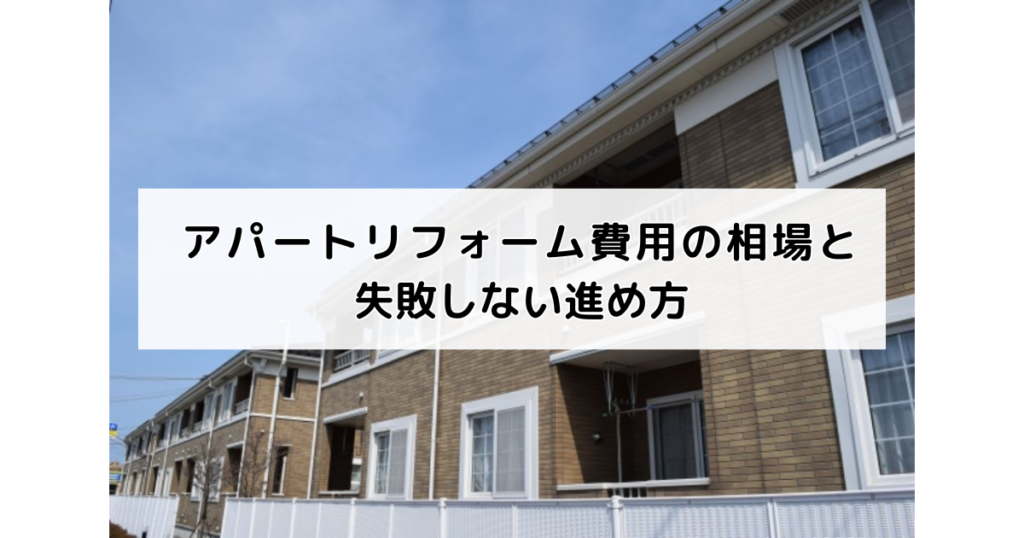セルフレベリングとは?費用・施工方法・種類まで徹底解説
目次
セルフレベリングとは?

「セルフレベリング」という言葉、聞いたことはあるけれど、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、セルフレベリングの定義、メリット・デメリット、用途などを詳しく解説します。
セルフレベリングの定義と仕組み

セルフレベリングとは、流し込むだけで自然に水平な床面を形成する材料、またはその技術のことです。
主に、コンクリートやモルタルなどの床下地の不陸(凹凸)調整に用いられます。
仕組みとしては、流動性の高い特殊な材料を使用し、重力によって自然に水平になろうとする性質を利用しています。
これにより、コテなどでの均し作業が不要となり、短時間で精度の高い床面を作ることができます。
セルフレベリングの用途と必要性

セルフレベリングは、主に以下の用途で用いられます。
- 床の不陸調整:古い建物の改修や、新築時のコンクリート打設後の不陸調整
- 床暖房の設置:床暖房パネルを設置する際の、平滑な下地作り
- フロアタイルの施工:タイルを綺麗に貼るための、下地調整
- バリアフリー化:段差をなくし、車椅子や高齢者でも安全に移動できる床面を作る
特に、古い建物の改修では、床の傾きや凹凸が原因で家具が安定しない、歩行時に躓きやすいといった問題が発生することがあります。
セルフレベリングは、これらの問題を解決し、快適な居住空間を作るために必要不可欠な技術と言えるでしょう。
セルフレベリングのメリット・デメリット
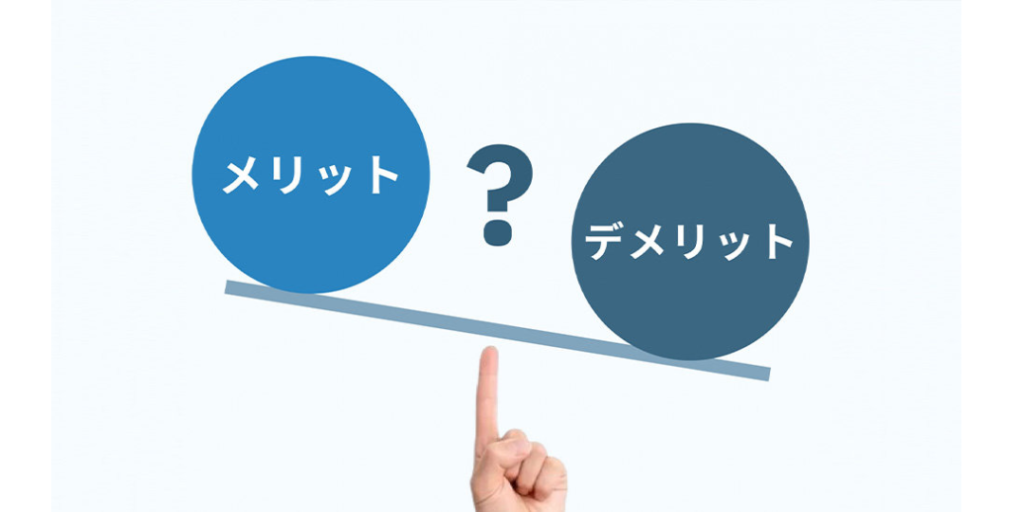
セルフレベリングには、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット:
・短時間で高精度な床面が作れる
・コテ作業が不要で、施工が比較的容易
・床暖房やフロアタイルの施工に適した下地を作れる
・バリアフリー化に貢献できる
デメリット:
・材料費が比較的高価
・一定の施工技術が必要
・撤去が困難な場合がある
・厚みを大きく調整する場合は不向きな場合がある
セルフレベリングの種類と選び方

セルフレベリング材の種類と特徴
セルフレベリング材は、大きく分けてセメント系と樹脂系の2種類があります。
それぞれの特徴を理解し、用途に合わせて適切な材料を選びましょう。
セメント系セルフレベリング材

セメント系セルフレベリング材は、セメント、骨材、混和剤などを主成分としており、強度が高く、耐久性に優れているのが特徴です。
主に、住宅や店舗などの床下地調整に用いられます。
メリット:
・強度が高い
・耐久性に優れている
・比較的安価
・施工後の収縮が少ない
デメリット:
・乾燥に時間がかかる
・樹脂系に比べて柔軟性が低い
・厚塗りには不向き
樹脂系セルフレベリング材
樹脂系セルフレベリング材は、合成樹脂を主成分としており、柔軟性が高く、薄塗りが可能なのが特徴です。
主に、商業施設や工場などの床仕上げ、または、床暖房用下地などに用いられます。
メリット:
・柔軟性が高い
・薄塗りが可能
・乾燥が早い
・耐薬品性に優れている製品もある
デメリット:
・比較的高価
・紫外線に弱い製品もある
・下地処理が重要
用途別セルフレベリング材の選び方
セルフレベリング材は、用途によって適切な種類が異なります。
- 住宅の床下地調整:強度と耐久性に優れたセメント系
- 店舗や商業施設の床仕上げ:デザイン性や機能性に優れた樹脂系
- 床暖房用下地:熱伝導率が高く、柔軟性のある樹脂系
- DIY:比較的安価で扱いやすいセメント系
DIY向けセルフレベリング材の選び方
DIYでセルフレベリングに挑戦する場合は、以下のポイントに注意して材料を選びましょう。
- 施工面積や厚みに合わせて材料を選ぶ
- 練り混ぜや流し込みがしやすい材料を選ぶ
- 乾燥時間や硬化時間に注意する
- 安全性や環境に配慮した材料を選ぶ
セルフレベリングの費用

セルフレベリングの費用相場
セルフレベリングの費用は、施工面積、材料の種類、厚み、下地の状態などによって大きく変動します。
一般的な費用相場は以下の通りです。
・材料費: 1㎡あたり1,000円~5,000円
・施工費: 1㎡あたり2,000円~8,000円
したがって、合計で1㎡あたり3,000円~13,000円が目安となります。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の費用は個別の条件によって大きく異なります。
見積もりを依頼する際は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
費用を左右する要因
セルフレベリングの費用は、以下の要因によって左右されます。
- 施工面積:施工面積が広いほど、材料費と施工費は高くなります。
- 材料の種類:樹脂系セルフレベリング材は、セメント系セルフレベリング材よりも高価です。
- 厚み:セルフレベリング材の厚みを厚くするほど、材料費は高くなります。
- 下地の状態:下地の状態が悪いほど、下地処理の費用が高くなります。
- 業者の料金体系:業者によって、料金体系が異なります。
DIYと業者依頼の費用比較
セルフレベリングは、DIYでも可能ですが、業者に依頼する場合と比較して、費用がどのように異なるのでしょうか。
- DIY:材料費のみで施工できるため、費用を抑えることができます。ただし、施工に失敗するリスクや、手間がかかるというデメリットがあります。
- 業者依頼:施工費がかかりますが、プロの技術で高品質な仕上がりが期待できます。また、施工後の保証が付く場合もあります。
DIYと業者依頼のどちらを選ぶかは、予算、技術、時間などを考慮して判断しましょう。
DIYの費用例
6畳の部屋(約10㎡)をセルフレベリングする場合
・材料費:10㎡×3,000円=30,000円
・合計:30,000円
業者依頼の費用例
6畳の部屋(約10㎡)をセルフレベリングする場合
・施工費用:10㎡×8000円=80,000円
・材料費:上記の30,000円
・合計:110,000円
セルフレベリングの施工方法

施工前の準備
セルフレベリングの施工を成功させるためには、事前の準備が非常に重要です。
下地処理:
・床面のゴミ、ホコリ、油分などを丁寧に取り除きます。
・ひび割れや穴などは、事前に補修しておきます。
・必要に応じて、プライマーを塗布し、下地とセルフレベリング材の接着性を高めます。
養生:
・壁際や柱など、セルフレベリング材が付着しては困る箇所を養生テープやビニールなどで保護します。
・セルフレベリング材が流れ出ないように、隙間を埋めておきます。
レベル出し:
・レーザーレベルや水準器などを使用して、セルフレベリング材の目標レベルを決め、印をつけます。
セルフレベリング材の練り方
セルフレベリング材は、製品によって練り方が異なります。
必ず製品の取扱説明書に従って、正確に練り混ぜてください。
計量:
・指定された量の水とセルフレベリング材を正確に計量します。
混合:
・電動ミキサーなどを使用して、均一になるまでしっかりと練り混ぜます。
・ダマにならないように、ゆっくりと材料を投入するのがポイントです。
静置:
・練り混ぜ後、数分間静置し、材料を安定させます。
セルフレベリング材の流し込み方
セルフレベリング材は、一度に大量に流し込むのではなく、少しずつ流し込むのがポイントです。
流し込み:
・低い場所から順に、セルフレベリング材をゆっくりと流し込みます。
・コテやレーキなどを使用して、材料を軽く均します。
気泡抜き:
・必要に応じて、気泡抜きローラーなどを使用して、材料中の気泡を取り除きます。
均し:
・自然に水平になるのを待ちますが、必要に応じてコテなどで表面を軽く均します。
養生と仕上げ
セルフレベリング材の養生時間は、製品によって異なります。
必ず製品の取扱説明書に従って、適切な養生を行ってください。
養生:
・施工後、セルフレベリング材が硬化するまで、歩行や重量物の設置を避けます。
・急激な乾燥や温度変化を避け、適切な環境で養生します。
仕上げ:
・セルフレベリング材が完全に硬化した後、必要に応じて研磨や塗装などの仕上げを行います。
セルフレベリングに関するよくある質問(Q&A)

セルフレベリングの乾燥時間は?
セルフレベリング材の乾燥時間は、製品の種類、気温、湿度などによって異なります。
一般的には、24時間~48時間程度で硬化しますが、完全に乾燥するまでには数日から1週間程度かかる場合があります。
- セメント系:比較的乾燥に時間がかかり、数日~1週間程度
- 樹脂系:比較的乾燥が早く、24時間~48時間程度
乾燥時間は、製品の取扱説明書に記載されているので、必ず確認してください。
また、気温が低い場合や湿度が高い場合は、乾燥時間が長くなる傾向があります。
セルフレベリングの上に何を施工できる?
セルフレベリングの上には、様々な仕上げ材を施工できます。
- フローリング:木質フローリング、クッションフロア、フロアタイルなど
- タイル:磁器タイル、セラミックタイル、天然石タイルなど
- カーペット:タイルカーペット、ロールカーペットなど
- その他:塗装、モルタル仕上げなど
ただし、仕上げ材の種類によっては、セルフレベリング材の種類や下地処理が必要になる場合があります。
仕上げ材のメーカーや専門業者に相談し、適切な施工方法を確認してください。
その他
Q:セルフレベリングの厚みはどのくらいまで調整できますか?
A:製品によって異なりますが、一般的には数mm~数cm程度です。厚みを大きく調整する場合は、複数のセルフレベリング材を重ね塗りする必要があります。
Q:セルフレベリングのDIYは難しいですか?
A:材料の特性や施工方法を理解していれば、DIYでも可能です。ただし、ある程度の経験や技術が必要になるため、不安な場合は専門業者に依頼することをおすすめします。
Q:セルフレベリングの耐用年数はどのくらいですか?
A:使用する材料や環境によって異なりますが、一般的には10年~20年程度です。適切なメンテナンスを行うことで、より長く使用することができます。
まとめ

この記事では、セルフレベリングの基本知識から、費用、種類、施工方法まで、幅広く解説しました。
セルフレベリングは、床の不陸調整や床暖房の設置など、様々な用途に活用できる便利な技術です。
DIYでも挑戦できますが、材料の特性や施工方法を十分に理解しておく必要があります。
この記事が、みなさまのセルフレベリングに関する情報収集の一助となれば幸いです。
セルフレベリングに関してご不明な点等ございましたら、お気軽に株式会社ベータまでお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。