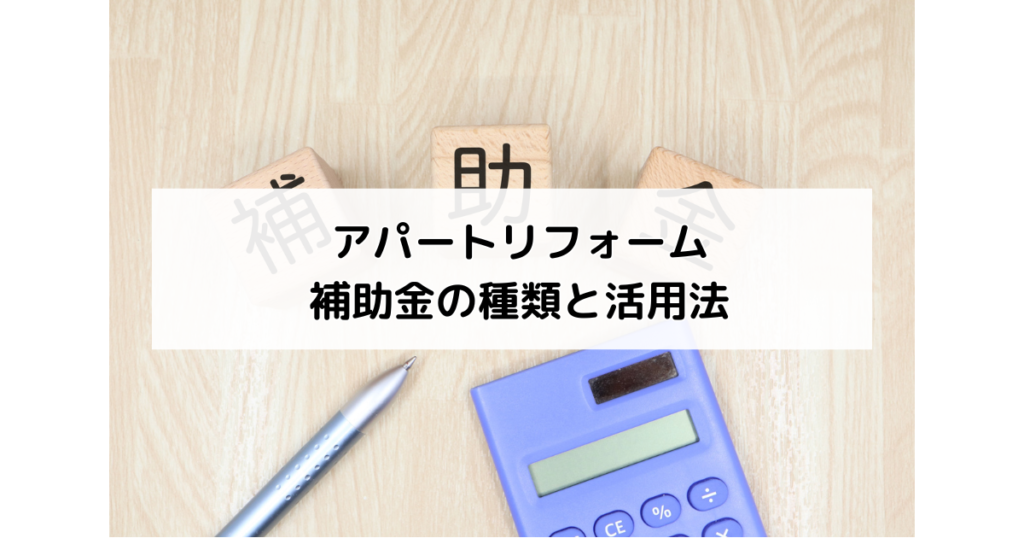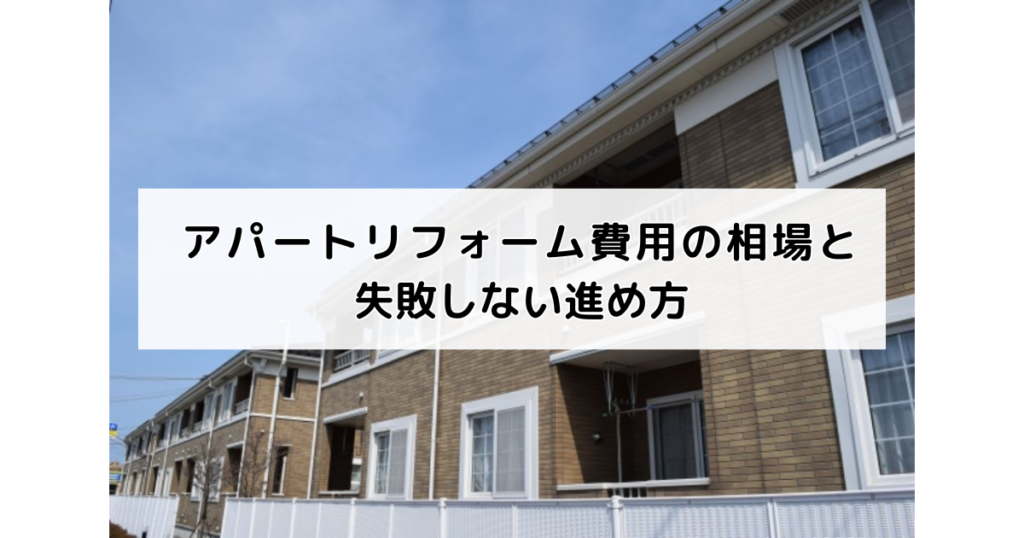マンションの畳とフローリングのリフォーム完全ガイド

マンションの畳やフローリングをリフォームするとき、「どちらに変えるべき?」「費用や工期はどのくらい?」「マンションならではの注意点は?」といった疑問を持つ方は多いでしょう。
実は、床のリフォームはお部屋の印象や快適さを大きく左右する重要なポイントです。畳の温もりを活かした和の空間も、フローリングのスタイリッシュでお手入れしやすい空間も、正しい知識と計画があれば理想の住まいに近づけます。
この記事では、「畳からフローリング」「フローリングから畳」それぞれのリフォーム方法・費用・メリットデメリットを徹底解説。さらに、マンション特有の注意点や業者選びのコツも紹介します。
マンションの床リフォームで失敗しないための完全ガイドとして、ぜひ最後までご覧ください!
目次
畳からフローリングへのリフォーム方法とポイント

和室を洋室風に変える第一歩として人気なのが、畳からフローリングへのリフォームです。見た目がスッキリするだけでなく、掃除のしやすさや家具の配置自由度が上がるなど、多くのメリットがあります。ここでは、主な施工方法から費用相場、工期の目安までを詳しく解説します。
畳をフローリングに変える主な2つの方法
畳をフローリングに変える方法は大きく分けて2通りあります。目的や予算、仕上がりの希望に合わせて最適な方法を選びましょう。
【方法1】畳を剥がしてフローリングに張り替える
最も一般的なのが、畳を撤去して床下地を整えた上でフローリングを張る方法です。畳の厚みはおよそ5〜6cmあるため、撤去後は床の高さを調整する「下地工事」を行い、床の強度と水平を確保します。
この方法は耐久性が高く、見た目・質感ともに本格的な洋室に仕上がるのが特徴です。賃貸では難しい場合もありますが、持ち家や分譲マンションなら長期的な満足度が高い方法です。
【方法2】畳の上にフローリングカーペットを敷く
もうひとつの方法は、既存の畳の上からフローリング風のカーペットを敷くタイプ。工事不要で、1日もかからず模様替え感覚で洋室風にできます。賃貸住宅でも原状回復しやすいため、気軽に取り入れられます。
ただし、畳の下に湿気がこもる可能性があるため、定期的に換気や除湿を行うことが大切です。
それぞれのメリット・デメリット
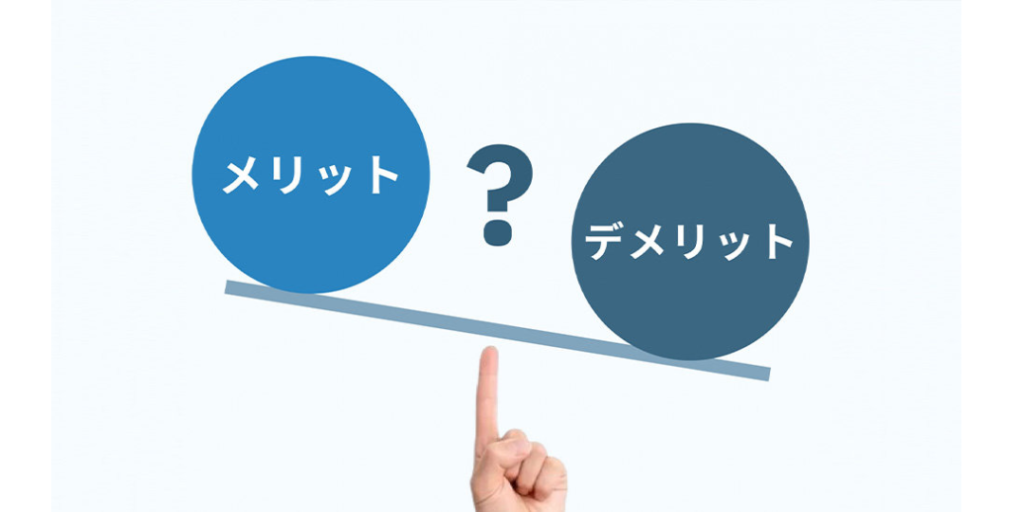
リフォームの目的や住まいの状況によって、どちらの方法が適しているかが変わります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
本格的な張り替えのメリット・デメリット
メリット:
・床下の状態をチェック・補修できるため、長持ちしやすい
・インテリアに統一感が出て、完全な洋室として仕上がる
・掃除がしやすく、ダニやカビの発生を抑えやすい
デメリット:
・工事費用が高く、1部屋あたり10〜20万円前後かかる
・工事費用が高く、1部屋あたり10〜20万円前後かかる
・工期が2〜3日程度必要で、家具の移動なども必要
上に敷くタイプのメリット・デメリット
メリット:
・費用を抑えられ、1〜3万円程度で施工可能
・工事不要で、DIYでも簡単に施工できる
・賃貸でもOKなケースが多い
デメリット:
・畳の弾力が残るため、床が柔らかく感じる
・湿気やカビのリスクがあり、長期間の使用には不向き
・フローリング風カーペットは経年劣化しやすい
費用相場と工期の目安
施工方法によって費用や工期が大きく異なります。ここでは、それぞれの目安を見ていきましょう。
業者に依頼する場合の費用
畳を撤去してフローリングに張り替える場合、6畳間で約10万〜20万円前後が一般的です。使用するフローリング材(無垢材・複合フローリングなど)や下地補修の有無によって金額は変動します。
工期は平均で2〜3日程度。古い畳の処分費用も含まれるため、見積もり時に必ず確認しましょう。
DIYで行う場合の費用・注意点
フローリングカーペットを敷く場合、材料費だけなら1万円台から可能です。ホームセンターやネット通販で簡単に入手でき、カッターでカットして敷くだけなので手軽です。
ただし、畳の状態が悪いまま施工すると、カビ・沈み込み・段差トラブルの原因になります。DIYの場合も、下地の清掃や除湿対策をしっかり行いましょう。
フローリングから畳へのリフォーム方法とポイント

近年、洋室中心の住まいが増えていますが、「やっぱり畳の落ち着く空間がほしい」という声も多く聞かれます。
フローリングから畳へのリフォームは、和の雰囲気を取り戻すだけでなく、断熱性や防音性の向上にもつながります。ここでは、主な方法や費用、注意点をわかりやすく解説します。
フローリングを畳に変える主な2つの方法
フローリングを畳に変えるには、「置き畳を敷く」か、「フローリングを撤去して畳を施工する」かの2つの方法があります。目的やコスト、居住状況に合わせて選ぶのがポイントです。
【方法1】置き畳を敷く
最も手軽なのが、フローリングの上に置き畳を敷くだけの方法です。サイズも豊富で、必要な分だけ購入して敷くことができるため、部分的な和スペースづくりにも適しています。
また、裏面に滑り止めが付いている製品も多く、賃貸住宅でも原状回復が簡単。畳の質感を気軽に取り入れたい人におすすめです。
【方法2】フローリングを撤去して畳を施工
もうひとつは、既存のフローリングを撤去し、下地を整えてから畳を敷く本格的な施工です。高さ調整や床下補修を行うため、見た目・耐久性ともに完成度が高く、純和室として仕上がります。
新築時のようなクオリティを求める場合や、長期的に和室を活用したい方に適した方法です。
それぞれのメリット・デメリット

どちらの方法も一長一短があります。ライフスタイルや居住年数を踏まえて選ぶと、後悔のないリフォームになります。
置き畳の手軽さと注意点
メリット:
・工事不要で、即日設置が可能
・必要な場所だけに敷けるため、アレンジ自由
・費用が安く、1畳あたり5,000円〜1万円前後
デメリット:
・段差ができやすく、掃除機がかけにくい場合がある
・通気性が悪く、湿気がこもるとカビが発生する可能性
・長期間使用すると畳がズレたり、色ムラが出やすい
本格的な和室化のメリット・デメリット
メリット:
・床下からしっかり施工するため、耐久性・断熱性が高い
・畳の厚みや素材を自由に選べる
・インテリア的にも統一感があり、本格的な和の空間に
デメリット:
・施工費用が高く、6畳で10〜20万円程度が目安
・工期が2〜3日かかる場合もあり、家具の移動が必要
・元に戻す際は再び工事が必要になる
費用相場と施工期間
施工方法によって費用も工期も大きく変わります。以下の目安を参考に、自分に合った方法を選びましょう。
DIYでできる置き畳リフォーム費用
市販の置き畳は、1枚あたり約5,000〜10,000円程度。
6畳分を敷く場合、約3万〜6万円前後で完了します。工事不要のため、届いたその日に施工可能です。
ただし、畳の下に湿気がこもらないよう、防湿シートや除湿マットを併用すると長持ちします。
業者施工の本格リフォーム費用
フローリングを撤去して畳を施工する場合、6畳で約10万〜20万円前後が一般的です。
使用する畳の種類(い草・和紙・樹脂など)や、床下の状態によって価格が上下します。工期は通常2〜3日程度で、撤去・処分費用も見積もりに含まれるケースが多いです。
床材選びで失敗しない!おすすめのフローリング・畳素材

床は住まいの「印象」と「快適さ」を大きく左右する重要な要素です。素材によって見た目や肌触り、メンテナンス性が異なるため、ライフスタイルに合った床材選びが失敗しないポイントです。ここでは、人気のフローリング材と畳素材の特徴をわかりやすく紹介します。
フローリング材の種類と特徴

フローリングは大きく分けて「無垢材」と「複合フローリング」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することで、長く快適に使える床を選びやすくなります。
無垢材の魅力と注意点
無垢フローリングとは、天然木をそのまま一枚板として加工したもの。自然素材ならではの木の温もりと香り、そして経年変化による味わいが魅力です。
素足で歩いたときの感触が柔らかく、冬でもひんやりしにくいのも大きなメリット。
ただし、湿気や乾燥の影響を受けやすく、反りや割れが生じることがあるため、室内環境の管理が重要です。また、定期的なワックスがけやメンテナンスも必要になります。
「質感重視」「自然素材の家にしたい」という方におすすめの素材です。
複合フローリングの特徴
複合フローリングは、合板の上に薄い天然木や化粧シートを貼り合わせた構造。無垢材に比べて反りや伸縮が少なく、メンテナンスが簡単なのが特徴です。
表面加工によってキズや水に強いタイプも多く、ペットや子どもがいる家庭でも安心。
デザインのバリエーションも豊富で、コストを抑えながら高級感を演出できるのが魅力です。無垢のような自然な風合いを求めつつ、扱いやすさを重視する場合に最適な選択肢です。
畳の種類とデザイン

一口に「畳」といっても、素材によって耐久性や見た目、メンテナンス性が大きく異なります。最近では伝統的な和室だけでなく、おしゃれな和モダン空間を演出できる畳も増えています。
イ草畳・和紙畳・樹脂畳の違い
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| イ草畳 | 伝統的な天然素材。香りがよく、調湿性も高い | 自然の香りでリラックス効果がある | 日焼けや湿気に弱く、色あせやカビのリスク |
| 和紙畳 | 和紙をこより状にして加工した人工素材 | 色あせに強く、お手入れが簡単 | 天然素材の香りや風合いはやや劣る |
| 樹脂畳 | 樹脂素材で作られた耐久性の高い畳 | 水拭き可能で、ダニ・カビが発生しにくい | やや硬めの質感で、温かみは少なめ |
特に近年人気なのが、和紙畳と樹脂畳。豊富なカラーバリエーションがあり、グレーやベージュなどを選べば洋室にも自然に馴染みます。
琉球畳でおしゃれな和モダン空間に
従来の畳よりも小さめで、縁(へり)がない正方形タイプの「琉球畳」。畳の目の方向を交互に敷くことで、市松模様のような陰影が生まれ、モダンでスタイリッシュな印象になります。
カラー畳との組み合わせも楽しめるため、リビングや寝室の一角に取り入れるだけで、デザイン性の高い空間を演出可能。
また、和紙畳や樹脂畳を使った琉球畳なら耐久性も抜群で、お手入れも簡単です。
地域ごとに異なる畳サイズと注意点

畳と一口に言っても、実は地域によってサイズが異なることをご存じでしょうか。
畳のサイズは部屋の寸法や建物の構造、さらには地域の慣習によって決まっており、同じ「6畳」でも広さが変わることがあります。リフォームや畳交換を行う際は、こうした違いを理解しておくことが大切です。
畳サイズの地域差を理解しよう
日本国内では主に「京間」「中京間」「江戸間」「団地間」の4種類の畳サイズが存在します。地域によって標準サイズが異なるため、間取り図の「◯畳」という表記だけで判断するのは注意が必要です。
京間・中京間・江戸間・団地間の違い
| 種類 | 主な地域 | 畳のサイズ(約) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 京間(きょうま) | 主に関西・九州 | 955mm × 1910mm | 最も大きいサイズ。ゆったりとした印象の和室に。 |
| 中京間(ちゅうきょうま) | 東海地方 | 910mm × 1820mm | 京間と江戸間の中間サイズ。中部エリアで主流。 |
| 江戸間(えどま) | 関東地方 | 880mm × 1760mm | 全国で最も普及している一般的なサイズ。 |
| 団地間(だんちま) | 北海道・東北・一部賃貸 | 850mm × 1700mm | 最も小さいサイズ。省スペース住宅で採用されやすい。 |
たとえば、同じ「6畳」でも京間は約10.9㎡、団地間では約8.7㎡と、2㎡以上の差が生じることもあります。
そのため、畳の交換やフローリングから畳へのリフォーム時には、現場の実寸確認が必須です。
サイズ確認の重要性とリフォーム前のチェックポイント
畳を新調する前には、必ず現地での採寸を行いましょう。
既製品の畳を購入する場合、地域標準のサイズと合わないことがあり、隙間や浮き上がりの原因になります。
チェックすべきポイントは以下の3つです:
- 部屋の実寸を測る(壁〜壁)
- 既存の畳サイズを確認する
- 建物の地域区分・築年数を把握する(古い住宅は独自寸法のことも)
リフォーム業者に依頼する場合も、「どの地域サイズで作られているか」を確認しておくと安心です。
畳の敷き方ルール
畳の並べ方にも、見た目の美しさや縁起に関わるルールがあります。特に「祝儀敷き」と「不祝儀敷き」という敷き方の違いは、知っておくと役立ちます。
祝儀敷き・不祝儀敷きとは
- 祝儀敷き(しゅうぎじき):
畳の四隅が1か所に集まらないように敷く伝統的な並べ方。
隙間が生まれにくく、縁起が良いとされ、住宅や茶室などで一般的に採用されます。 - 不祝儀敷き(ふしゅうぎじき):
畳の四隅が1点で交わる敷き方。法要や弔事などの場に使われることが多く、日常の住まいでは避けるのが一般的です。
縁起の良い配置で快適な空間づくり
畳の敷き方は単なるデザインではなく、「気の流れ」や「空間の調和」を整える役割があります。
祝儀敷きにすることで、部屋全体のバランスが取れ、落ち着いた雰囲気に。
また、畳の向きを交互にすることで光の反射に陰影が生まれ、高級感のある和の空間を演出できます。
マンションでの床リフォームの注意点

マンションの床リフォームは、戸建てと違い建物全体でのルールや制約が多く存在します。
特に「防音性能」や「施工音による近隣トラブル」などは、事前確認を怠ると後々のトラブルにつながることも。
ここでは、マンションならではの注意点や、失敗しない業者選びのコツを詳しく解説します。
マンション特有の制約
マンションの床リフォームでは、管理規約や構造上の制限により、自由に施工できない場合があります。特に防音性能(L値)に関するルールは、ほぼすべてのマンションで定められています。
防音規定(L値)と管理規約の確認
多くのマンションでは、「L値」と呼ばれる遮音等級によって、フローリング材の防音性能が指定されています。
L値とは、床の衝撃音をどれだけ軽減できるかを示す指標で、数値が小さいほど防音性能が高いことを意味します。
| L値の目安 | 性能レベル | 特徴 |
|---|---|---|
| L-40 | 高い遮音性能 | ほとんど音が響かない。上階の生活音がほぼ気にならない。 |
| L-45 | 一般的な防音レベル | マンションの多くで採用されている。 |
| L-50以上 | 低遮音性能 | 足音や物音が階下に伝わりやすい。 |
リフォーム前には必ず管理規約を確認し、「使用できる床材の防音等級」を把握しておきましょう。
また、フローリングから畳・カーペットへ変更する場合も、防音性能の基準に合っているかをチェックすることが重要です。
施工時の騒音・近隣トラブルを防ぐ方法
リフォーム中は、工事音や資材の搬入音がどうしても発生します。
近隣とのトラブルを避けるために、以下のような対策を取ると安心です。
- 施工前に上下左右の住戸へ工事予定を伝える
- 管理組合に工事申請書を提出し、承認を得る
- 工事時間帯の制限(例:9時〜17時)を守る
- 工事中の廊下・エレベーターへの養生(保護)対策を徹底する
こうした配慮を行うことで、リフォーム後のご近所付き合いも円滑になります。
業者選びとトラブル回避

マンションの床リフォームは、構造や規約の理解が欠かせません。経験の浅い業者に依頼すると、防音基準違反や管理組合とのトラブルに発展するケースもあります。
リフォーム会社選びのポイント
業者を選ぶ際は、以下の点をチェックしましょう。
- マンションリフォームの実績があるか
- 管理組合との調整を代行してくれるか
- 防音フローリング(L-45など)の施工経験があるか
- 工事保険(損害賠償保険)に加入しているか
また、ショールームで実際の踏み心地や防音性を体感しておくのもおすすめです。見た目だけで判断せず、生活音対策やメンテナンス性も含めて比較しましょう。
見積り比較と契約時の注意点
同じ床リフォームでも、施工範囲や防音材の有無によって費用が大きく変わります。
複数の業者から見積もりを取り、以下の点を確認しておくことが大切です。
- 「防音等級(L値)」が明記されているか
- 「既存床の撤去費」「廃材処分費」が含まれているか
- 「工期」「施工時間帯」「保証内容」が明確か
また、契約前には管理組合の承認を得てから着工するようにしましょう。
承認前に工事を進めると、やり直しや罰則の対象になる場合もあります。
東海エリアのマンションリフォームはベータにお任せください!

東海エリアでマンションリフォームを検討している方は、地域密着型のリフォーム会社「ベータ」にぜひお任せください。
私たちは、名古屋市を中心に愛知・岐阜・三重エリアで多数の実績を持ち、マンション特有の構造や管理規約を熟知した専門スタッフが、最適なプランをご提案します。
「壁紙と床を一新して明るい空間にしたい」「中古マンションを理想の住まいにリノベーションしたい」など、お客様のライフスタイルやご希望に合わせたオーダーメイドのリフォームを得意としています。
現地調査からお見積り、施工、アフターサポートまで一貫対応するため、初めての方でも安心してお任せいただけます。
さらに、補助金・助成金の最新情報にも精通しており、費用を抑えたリフォームもご提案可能です。
東海エリアでのマンションリフォームなら、実績・提案力・安心サポートのすべてが揃う「ベータ」にご相談ください!
まとめ

マンションの床リフォームは、素材選び・工法・費用・施工ルールなど、戸建てとは異なるポイントをしっかり押さえることが大切です。
畳からフローリング、またはフローリングから畳への変更も、それぞれにメリット・デメリットがあり、ライフスタイルや部屋の用途に合わせた選択が成功の鍵となります。
また、マンション特有の防音規定や管理規約の確認を怠ると、工事ができなかったり、近隣トラブルに発展するケースもあります。リフォーム前には、必ず業者と一緒に事前チェックを行いましょう。
信頼できるリフォーム会社に依頼すれば、デザイン性と機能性を両立した理想の住空間を実現できます。
東海エリアでマンションリフォームをお考えの方は、地域密着で実績豊富な「ベータ」にぜひご相談ください!